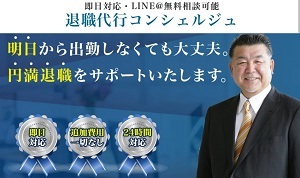職場の上司にこんなことを言われたんだけど、これってパワハラ?
学校のいじめはよく騒がれていますが、人間関係のいざこざは子供に限った話じゃありません。
大人の世界でも、いじめや嫌がらせなどの『ハラスメント』が深刻な問題となっています。

ちょっと過敏反応しすぎでしょ!ってくらいにね
以前は会社内で済んでいた問題も、Twitterやインスタをはじめとする、SNSの普及で社会全体の問題として共有されるようになりました。
とくに職場で発生しやすい『パワーハラスメント』は、他人事ではないという人も多いでしょう。
被害者意識を強く植え付けられた現代では、誰もが被害者にも加害者にもなり得るんですよ。
大半の人はどちらの立場になるのも、遠慮したいと思っていますよね。
そこで当記事では
◎部下を持つ立場になるにあたり、ハラスメントを未然に防ぎたい
という人に向けて、職場でパワハラだと判断されやすい行為を、事例も含めて詳しく解説します。
パワハラ予防に向けて知識をつけておきたい!という人は、ぜひご参考あれ。

パワーハラスメント/パワハラの定義とは?

厚生労働省では平成24年3月に「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を次のようにまとめています。
ハラスメントとは「同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為」と定義されています。
またハラスメントの裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、6つのハラスメントを典型例としています。
1、 身体的な攻撃/暴行や傷害
2、 精神的な攻撃/脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3、 人間関係からの切り離し/隔離・仲間はずれ・無視
4、 過大な要求/業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5、 過小な要求/業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6、 個の侵害/私的なことに過度に立ち入ることなおこの典型以外にも職場でのパワーハラスメントに当たりうる行為は存在します。
*出典 厚生労働省「職場のパワーハラスメントについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html
定義の中にも示されている通り、職場でパワーハラスメントが行われていると、職場の雰囲気が格段に悪くなりますよね。

何でまだ誰も契約取れてねぇんだよ!!

取れるよう部下を指導なりして、成果を出すのが上司の役割だぞ?
日常的にパワハラが横行する職場環境では、会社全体の業務効率性も落ち、売上にも悪影響を与えかねません。
そのため最近では、コンプライアンスの一環として
「パワハラ研修」を取り入れている企業も増えています。
また企業のパワハラ対策が義務化されることもあり、職場でのパワハラ問題は今後さらに過熱していくでしょう。

職場で部下にパワハラと言われる行為48選
意図的に行うパワハラもあれば、無意識のうちにパワハラと思われていることもあります。
パワハラの定義で厄介なのは、行為の内容に関わらず『受け手がパワハラと言えばパワハラ』というような、かなりのひいき目があるところ。

正当な指導でパワハラだと言われたら、たまったものじゃありません。
いずれにせよ
『自分がしていることはパワハラだ』
と自覚・理解することが難しいケースも多いのです。
何故なら『パワハラ行為』の範疇が
人・時代・状況によって異なったり、変動するから。
だって、他人からされて嫌だと思う言動なんて
人や状況によって異なるでしょう?
明確な罵詈雑言なら別ですけど。

◎イケメンの壁ドンならOK
◎ブサメンの壁ドンならNG
みたいなね。
とりあえず、職務上の地位を利用して『他者に肉体的・精神的な苦痛を与える言動』が
総じてパワハラと言われるのが現代の価値観です。
中には「こんなことまでパワハラになるの?」という事例もあります。
しかし、昔は当たり前だったこと、社会とはそういうものといった考え方も
通用しなくなりつつあるのが現代なんです。

一方ガチのパワハラとして、問題になる行為をしている上司が多いのもまた事実。上司の役割は部下の能力を引き出し、活用することなので、怒鳴る・追い詰めるなどしかできない上司はただの無能です。
仕事上の立場や上下関係を利用したパワハラ

上司から部下に対して行われるパワハラ、または立場の優位性を利用して行われるパワハラです。
①嫌がる仕事を意図的に多く与える
仕事を管理する上司が、特定の個人にばかり本人の適性や効率を無視して、過剰な仕事を与え続けるのはパワハラです。
他の人と比べて明らかに多すぎる業務を与え『なぜできないんだ!』と責め立てる光景、皆さんもイメージしやすいと思います。
②業務を常に監視して圧力をかける

常に監視されている状況で仕事ができる人がいるでしょうか?
管理と監視をはき違えている人に多いパワハラ。
常に監視することは、相手にプレッシャーやストレスしか与えません。
③業務上、必要な知識や情報を与えない・教えない
職人の世界ではよく
「習うより慣れろ」「技術は教わるのではなく盗む」
などと言われます。
一理あるのでしょうが、師匠と弟子の信頼関係があってこその言葉。
上司として部下に教えるべきことを教えないのは、手抜きか意図的な嫌がらせです。
④本人の希望を無視した配属や異動を行う
会社のため、経験のため、とはいえ本人の意向をよく聞いて話し合うことが必要です。
また介護や家庭の事情などの問題を抱えている場合もあります。

ただし、自分の希望が通らないからパワハラだ!というのも横暴です。個人には個人の事情があるように、会社には会社の都合があります。双方納得の上で決定することが大切です。
⑤業務に対する正当な評価をしない
成果に対する正当な評価をせず、褒める・昇給・賞与など何ら還元を行わない行為。
上司の役割は部下を育てる・活かすことなので、褒める・認めることも重要な仕事のひとつです。
⑥意図的に仕事を与えない
会社に出社させるのに仕事を与えない、典型的なパワハラです。
一般的にこのような状態を「社内失業」「社内ニート」などと表現します。
仕事が与えられないことで社内での孤立を招いたり
本人の資質の問題にすり替えられて低評価や降給の理由にされたり
さらなる悪影響を及ぼします。
⑦不当な評価による降格や降給を行う
人事権の濫用以外のなにものでもありません。
誤った評価や査定は裁判では無効になります。
⑧必要なサポートやフォローをしない
必要なサポートやフォローをするのが上司の仕事。
それができないのであれば、現場で働き続けるしかありません。
現場プレーヤーの仕事とマネジメントは全くの別物です。
⑨部下からの相談に耳を貸さない
部下の話を聞くことも上司の仕事の一環です。
話を聞かないことで業務に支障が出て
「なぜちゃんと話さなかったのか?」などと責める上司も少なくありません。
⑩体調不良などに対する配慮をしない
健康管理は社会人の基本とはいえ、不意の病気やケガは誰にでも起こります。
十分に休養を取って回復・復帰できるようにサポートするべきです。
休ませない、体調不良による欠勤を理由にその後の対応が悪くなる、などは論外。

そういう上司に限って、自分の体調不良時はすぐ休むんですよね
⑪退職を促すために不当な異動や転勤を命じる
異動命令が違法であり無効になるのは、以下に当てはまる場合です。
・嫌がらせが目的である
・パワハラが目的である
・自主的な退職を促すことが目的である
・その他、合理的な理由が一切ない*出典 「労働問題弁護士ガイド」
https://roudou-bengoshi.com/haiten/1044/
ただしこれらを立証する確固たる証拠が必要です。
⑫集団の前で叱責してさらし者にする
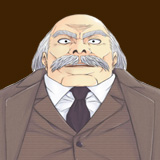
何であんな失敗したんだ!言ってみろ!!

すいません・・・
部下の社内での人間関係を崩壊させかねないパワハラです。
またこうした叱責を目にする周りの人間にも、無言のプレッシャーや「次は自分かも?」という怯えや萎縮を与えます。
⑬マッサージや肩もみなど個人的な雑用を命令する

パワハラでありセクハラでもある行為です。
マッサージや肩もみをさせる言い訳にコミュニケーションを持ち出す人もいますが、そんなコミュニケーションは職場に必要ありません。

恋人同士でやってくれ
罵声や暴言など言葉によるパワハラ
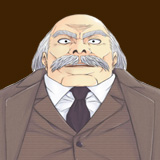
アホ!ボケ!オタンコナス!お前のかーちゃんデベソ!

ボキャブラリーの低さよ
大声で罵声を浴びせたり暴言を吐いたりすることは、暴行罪と判断されることもあります。
⑭失敗やミスに対して大声で怒鳴りつける
注意する声が段々と大声になってしまうのと、大声で相手をやり込めているのとでは明らかに違います。本人は無自覚でも周りで聞いていればわかりますよね。
⑮人格や性格をけなす罵声や暴言を吐く
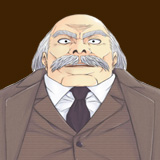
お前は人として終わってるよね。そんなんだから結婚もできないんだよ

人として何がどう終わっているのかご説明いただこうか
失敗に対する叱責や注意はある程度仕方ないかもしれませんが、冒涜と指導・叱責の境目は非常にあいまいです。行動・行為に対しての注意は必要ですが、性格・人格の否定は指導上必要ありません。
⑯給料泥棒!仕事辞めれば?役立たず!などと言う
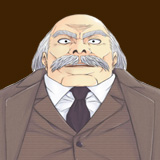
給料泥棒!仕事辞めれば?役立たず!

(上司として)給料泥棒!仕事辞めれば?役立たず!
極端な成果主義や体育会系の上司や会社に多いパワハラ。
会社を辞めろと言われて辞めた場合、ほとんどは自己都合による退職とみなされ、再就職の支障が出ることもあります。

前職を辞められたご理由は?
じつは労働基準監督署や職業安定所などでパワハラがあって辞めたことを相談すると、会社に確認の上で会社都合の退職に変わる可能性も。
そもそも労働者に対して退職を勧める場合は、決して強制をしてはいけないことになっています。
また解雇する場合には、30日以上前に解雇の予告をしなければいけません。
予告なしに解雇をした場合は30日以上分の賃金を払う必要があります。
⑰死ね・殺す・消えろなどの暴言を吐く
ここまでくると言葉による犯罪であり、著しい人格への攻撃です。
言われた日時のメモや暴言の録音をするなどして、社内の相談先か外部の相談機関などでパワハラの証拠として役立てましょう。

普通に脅迫罪で訴えられるレベル
⑱不細工!モテないだろうなど外見に対する悪口を言う
体型や顔立ち・服装などに対する悪口で、相手を貶めるパワハラ行為。
単純な悪口であり、異性間ではセクハラにも該当します。
物理的・精神的な暴力によるパワハラ

暴力が必要な仕事なんてありますか?

まあ裏の仕事ならあるいは…
刑法上、傷害罪や暴行罪にあたり得る事態です。
すぐに専門機関などに相談しましょう。
⑲物にあたって大きな音を立てる
大きな音で周囲を委縮させてしまうパワハラの一種。
本人が個人的にイライラしてやった行為でも、不快に感じる人がいるんです。
小さな子供でさえ物にあたってはいけないと教育されています。
⑳殴る・蹴る・叩くなどの暴力行為
暴力行為は社会性を持つ人間の仕事には不要なものです。
格闘技などであれば別ですが、一般企業において暴力を振るう上司は、暴力でしか人を動かせない無能ということになります。
㉑大声でプレッシャーをかける
ひと昔前はこの手法を用いる企業が数多く見受けられました。
大声でのプレッシャーは暴力と同じく、音による本能的な萎縮や恐怖を与える行為。

こうした単純な方法でしか成果を出せないのであれば、その上司は現代の社会で生き残れない人材と言えるでしょう。
また今の世の中で過剰な大声は「脅し」にもつながります。
㉒ミスをした時に社内共有メールなどで実名をさらす
部下のミスを引き受けてフォローする、今回のミスを次回へと活かせるよう指導するのが上司の役割です。
㉓休むのはいいけれどノルマ達成できるの?と暗に休日出社を強制する
休日出勤は振替休日の取得など、会社の就業規則や雇用契約の内容によるケースもあるため、一概にパワハラとは言えません。また仕事の進捗具合などで判断する、という人も多いでしょう。
問題なのは、休日の度に同じような言葉で詰めてくるパワハラ上司です。
休日出勤を強制されるたびに、代休や休日出勤手当の確認を書面でもらうようにしましょう。
◎会社が認めた休日出勤なのか
◎上司の一存によるものなのか
あとになって問題視された時の証拠になるからです。
㉔物やタバコなど危険物を投げつける
一歩間違えれば生命の危険さえある行為です。
ケガをした場合は診断書、そうでない場合でもしかるべき証拠を押さえておきましょう。
集団から孤立させるパワハラ
部下の社内での立場を失くし、存在そのものを否定するようなパワハラです。
上司の顔色を伺うあまり、同調する社員が出ないとも限りません。

大勢が少数を攻撃する、いじめの典型的な構図でもあります。
㉕ほかの社員の前で怒鳴りつける

注意・叱責は必要かもしれませんが、人前でわざわざ怒鳴る行為には何か別の意図を感じます。
㉖○○みたいにならないように!などダメ社員の代名詞にする
一昔前の学校や会社では、割とよく見受けられた光景。
しかし、実際は組織のために個人を貶める行為であり、例え該当する部下が本当に使い物にならないほど役立たずであったとしても、社内全体に広げてはいけません。
㉗意図的に会話を成立させない
仕事に支障が出るだけです。
㉘ほかの社員にも会話をしないように根回しをする
組織の中で自分が気に入らない相手を全員で阻害するように!って行為は、小学生や中学生で卒業しておきましょう。上司として人の上に立つなら、人としての大きさも器も重要です。

組織全体に広げたところで、自己満足にしかならず、業務効率が落ちるだけ。
㉙根も葉もない噂を流す
無視するに限ります。
行き過ぎるようなら、全て録音して名誉棄損で訴えるべし。
㉚電話やメールを無視して報連相を成立させない
ビジネスの基本である「報連相(ほうれんそう)」
本来は《報告・連絡・相談がしやすい職場環境を作りましょう》という意味だとか。

だからと言って、自分が報連相できないのは上司のせいだ!と開き直るのも問題だからね?
上司が報連相を無視するというパワハラは、結果的にトラブルが発生して、自分が尻ぬぐいすることになるだけです。
㉛ほかの社員と差別してあからさまな態度を取る
上司と部下の間にも相性や好き嫌いはあります。
基本は組織での業務なので割り切るしかありません。

相手を変えようとするより、自分が変わるほうが楽ですぞ。
ただあまりにもひどい場合には、別の上司や人事部等に相談をしましょう。
㉜飲み会などに1人だけ誘わない
パワハラ上司がいる飲み会に行ってもロクなことはありません。
貴重な時間とお金の無駄使いをしなくて済んだくらいに割り切りましょう。

何度か誘っても「行きたくない!」と言い続ける割に、誘わないようになると「誘ってもらえない!」と文句を言い出す、よく分からない部下もいるんだとか。
プライベートを犠牲にさせるパワハラ
かつての日本では『プライベートを犠牲にしても会社に尽くす』という風潮がありました。
終身雇用制や年功序列制が成り立っていた時代に育った上司ほど、部下のプライベートを軽視する傾向にあるようです。
しかし、現代ではそのような考え方、働かせ方はパワハラに当たります。

上司に気に入られることでやりやすくなることもあるけど、出世するメリットもなければ、比例した収入アップもない現代ですからね。
㉝残業を強制する
残業については会社の就業規則や雇用契約に準じます。
一般的には時間外労働をする確固たる正当な理由がない場合は、残業を強制できません。
業務上、緊急で必要でもないのに部下に残業を強制するのはパワハラです。
㉞仕事が終わらないからと休日出勤を強制する
パワハラ事例㉓同様です。基本的に労働者は拘束時間が定められています。これは仕事ができない人・できる人に関係ない法律です。
明らかに労働基準法に反している、休日出勤の強制ばかりで体調を崩した、などの場合は労働基準監督署に相談しましょう。
㉟終業後のイベントや飲み会に強制参加させる
部下は上司の遊び相手ではありません。
事情を考慮せず強制的に参加させるのはやめましょう。
飲み会も部下には仕事の一環と感じられ負担を感じる人もいます。
「親睦のため」と言いながら部下のプライベートを奪うのはパワハラになります。

親睦もそこそこには必要ですが、部下のタイプや会社の仕組みにもよりますね。
㊱翌日、仕事なのに朝まで帰らせない
朝まで飲んでそのまま仕事なんてナンセンスです。
というか朝までプライベートを拘束してる時点で、色々問題あり。
㊲休日の電話やメールに応じることを強制する
あまり知られていませんが(有名無実化していますが)、休日や業務時間外の業務連絡は労働基準法でも禁止されています。

とはいえ、必要な連絡は必要だから仕方ないんですけどね。
プライベートを侵害するパワハラ
部下のプライベートを監視・詮索・侵害するパワハラ行為。
あくまでパワハラとしてしますが、同僚や友人同士でも問題視される内容ばかりです。
㊳スマホを無断で覗く・見る・いじる
プライベートの大いなる侵害です。
普通に親しい間でもないのに無断で触るなし。
㊴デブ・太ったなど身体的な特徴をからかう
名誉棄損・パワハラ・セクハラなど、複数の違法行為に該当する恐れがあります。

ただし上司と部下の関係性によっては容認されることもある。難しい。
㊵化粧が濃いなどプライベートなことに口を出す
100%余計なお世話です。(とある女性よりご意見いただきました)
TPO上の教育や指導であるとしても、言い方を間違えればパワハラです。
㊶彼氏・彼女いないの?といらぬ詮索をする
同性同士であってもセクハラになります。
まったく仕事に関係がない上に極めて個人的なことです。
㊷お見合いや合コンを本人の意思なく設定する
興味がなければハッキリと断りしましょう。
昨今のご時世は結婚よりも、自分の自由を重視する若者が多いことを理解しておいてください。
㊸休日や休暇に業務とは無関係の連絡をする
パワハラ事例㊲同様、違法を問われかねません。
㊹休日に無理やり遊びに誘う
休みは休むためにあるものです。
行く必要も行かなければならない理由もありません。

もちろん行きたければ行ってください
違法行為を強制するパワハラ
違法行為という認識の有無に関わらず、させた側も従った側も両者とも罪に問われる可能性があります。
もはやパワハラという名の犯罪です。
㊺飲み会で飲酒をした後に運転を命じる
断固として断りましょう。
道路交通法65条の第3項の「何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、種類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」
*出典 「飲酒運転の罰則等」警視庁
に明確に違反します。
また飲酒の上で事故を起こせば運転手と共に懲役や罰金が科せられます。
㊻ゲームなどで異性の社員に触れるように命じる
セクハラの強要です。
迷惑防止条例では相手の同意がなく手を握っただけでも処罰の対象となり得ます。

まず今時そんなゲームやる…?
㊼顧客を騙してでも契約を取るように命じる
「詐欺」という犯罪です。
上司だけの考えか、会社ぐるみの考えか
いずれにせよ、真っ当な考え方の会社ではありません。
迅速に転職先を探しましょう。
㊽法律上で違法とされている行為を命じる
上司や会社が命じたことであっても、違法なことをして真っ先に罰せられるのはあなたです。
倫理的に従えないのであれば、その意思をしっかり伝えるべきでしょう
部下から上司への逆パワハラ
ここまでは上司から部下へのパワハラ事例を紹介してきましたが、最近では部下から上司への逆パワハラも増加傾向にあります。

法に守られているという立場を利用して、上司に対して無茶やワガママを押し通そうとする部下が増えているんです。
増加傾向にある逆パワハラ
パワハラと言えば
◎正社員から非正規社員
などの関係性でのみ発生すると思われがち。
しかし、パワハラ全体の5%近くは、部下から上司への逆パワハラなんです。
しかも、この比率は年々増加しているとか。

何故でしょうねぇ
会社の対策遅れが目立つ逆パワハラ
企業でコンプライアンスの一環として行われる「パワハラ研修」は、そのほとんどが『上司から部下へのパワハラ』という認識のもとで行われています。
社内で逆パワハラが起こっていても、気づいていない企業は少なくありません。
理由としては、以下のような背景があるためです。
ようは部下が嫌がる行為を何でも『パワハラ』だと国が擁護するから、部下側が調子に乗って『都合の悪いことは、何でもパワハラだと言えばいい』という、考えを持ちだしているということ。

ゆとり教育で体罰禁止を過剰に喚起した結果、子どもたちが教師に対して強気に出だし、なおかつ叱られると『傷ついた!精神的な体罰だ!』と言い出したようなもの。国もいい加減学べよと思う。
また終身雇用制や年功序列制から実力主義に移った現在では
年齢・役職・雇用形態に関係なく部下のほうが業務上で力を持つ場合も多く
逆パワハラが起こりやすくなっています。
とくに中間管理職などは部下とのトラブルを避けたいあまり、自身が逆パワハラを受けていても相談しづらい傾向にあります。

つまり国や政府が介入したことで、部下と上司の力関係及び、攻守が逆転しただけって話です。
よくある逆パワハラ行為3選
パワハラと同じく、逆パワハラにも多くの事例があります。
ここでは代表的な逆パワハラの事例を紹介します。
①パワハラで訴えると脅す
冗談にせよ本気にせよ、部下にこの言葉を言われたことがある上司は多いはずです。
それほどにパワハラという言葉は浸透しました。
実際にパワハラが行われることはいけないことですが、あれもこれもパワハラと騒げば上司がおとなしくなると勘違いをしている部下も困ります。
適切な注意や指導でも、パワハラと言われたら上司は部下に対して何も言えなくなってしまいます。
②身体的特徴や年齢を攻撃する
身体的な特徴や年齢・世代をあげつらって、上司を精神的に追い詰める典型的な逆パワハラです。
③SNSを使って攻撃する
SNSやブログに上司の実名や写真などを公開して、誹謗中傷するケースもあります。
パワハラ上司と呼ばれないための方法
パワハラが社会問題化している現代ですが、パワハラを気にするあまり部下との関わり自体が困難になってしまうのも問題です。
一方でパワハラの予防や対策の重要性は理解していても

権利ばかり主張されるのではないか?
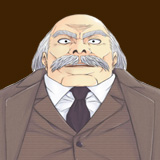
円滑なコミュニケーションが取れなくなる
などの不安を抱えている企業も多いです。
上司はもちろん、会社としてもパワハラに対する最低限の対策はしておかなければなりません。
具体的には以下のような方法でパワハラ呼ばわりの対策が可能です。
言葉を選んでパワハラ呼ばわり対策
「言葉」によるコミュニケーションは非常に難しいものです。

キチンと言葉にしたつもりなのに、相手に自分の真意が伝わらなかった
というような経験は誰にでもありますよね。
同じことを伝えていても
Bさんの伝え方では指導
なんて解釈をされるケースも少なくありません。
相手がどう受け取るかにより、ひとつの言葉からいくつもの意味が生じます。
つまり、選ぶ言葉次第でパワハラ呼ばわりの回避も可能ということ。
部下との関係で何よりも避けるべきなのは
侮辱的な言葉、名誉を傷つける言葉、人格を否定するような言葉です。
同じ意味でも伝え方でパワハラ呼ばわりを回避できる
言葉を選ぶと同じくらい話し方も重要です。
冷静に普段通りのトーンで伝えるようにします。
感情的になって大声を出したり高圧的に話したりしてはいけません。
それでは相手は委縮するばかりで、肝心の話は少しも伝わらないままです。
また部下一人に対して複数人で話すようなことも避けましょう。

基本的に一対一、他人の目に入らない個室などで話し合うのが理想です
感情を封印してパワハラ呼ばわり対策
上司とはいえ感情的になってしまうこともあるでしょう。
嬉しいことならばいいのですが、部下への注意や指導の場面で感情的になってはいけません。
感情のままぶつけてしまうと、自分でもコントロールが効かなくなってしまう恐れがあります。
まずは自分の中で整理してから、冷静に対処できるようになってから伝えるようにしましょう。
ミスの叱責などはあくまで冷静に言葉や態度を選んで行う
ミスが起こった時に大切なのは、同じことを繰り返させないことです。
ミスが起こった原因、ミスの原因や対策をロジカルに伝えてあげることが上司の役割です。
怒りに任せて叱責が人格を否定する、ただの悪口にならないよう注意しましょう。
コンプライアンスを徹底してパワハラ呼ばわり対策
パワハラは職場など他人ありきの環境で発生する問題です。
そのパワハラを防ぐには、自分一人が対策方法をわかっていればいいというものではありません。
同じ部署やチームの仲間とパワハラに対する認識を共有しておくことも、パワハラ発生予防に有効な方法です。
部下からパワハラの指摘があった場合
自分に明らかに非があった場合には謝罪・改善します。
しかし、適正な指導を行ったのに『パワハラではないのか?』と言ってくる部下に対しては、変に気弱にならず、毅然とした対応で臨みましょう。
まずは会社(上司)に報告をし、部下が納得するまで話し合いの場を設けます。
逃げたり誤魔化したりせず、信頼関係の再構築に正面から向き合うようにしましょう。

仮に訴えられたとしても、業務上必要な指導であると認められれば、罰せられることもありません。
まとめ
職場からパワハラがなくなるのを望むのは当然ながら、状況によっては自身で解決すべきケースも少なくありません。
個人的に『いじめ』や『パワハラ』の対策には、以下のような種類があると思っています。
◎当事者同士の接し方の調整で解決すべきレベルのいざこざ
◎部下側の被害意識が強すぎるだけな正当な指導
本来、パワハラ対策として会社が気にするべきは一番上の項目だけです。
それがなぜか二つ目まで対処するのが義務化しつつあり、もはや部下と上司という関係性の価値がなくなりつつあります。
立場の違いはあれど、組織に属する以上は時に厳しい言葉や状況もあるでしょう。
部下が辛いと感じること=パワハラと判断していては、組織は成り立ちません。

管轄すべきパワハラの範囲・対策の範囲は、しっかり吟味したほうがいいと思います。